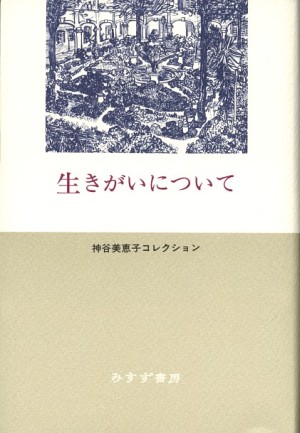 この本は、僕が生まれた年に出たようです。ずいぶん昔の本ですが、そういった古臭さは一切感じられません。
この本は、僕が生まれた年に出たようです。ずいぶん昔の本ですが、そういった古臭さは一切感じられません。ハンセン病で隔離施設で暮らしている人、死刑囚、死を目前にした病人、そういった究極の場に置かれた人の眼を起点に、「生きがい」とは何かを考え、そしてそこから広くわれわれ一般の「生きがい」を考えたエッセーです。
夢や目的が生きがいだと言うのではなく、何か前に向かって進むこと、そういった生を営むこと自体が、いきることの「はり」になり、生きがいになることもあると言います。極端にいえば、目標が達成されなくてもいい。定年退職した人にとって、「きょういく=今日行く」ところがあるということが重要なのだ、という話を思い出しました。
また、後半では宗教的な面から生きることの意義についても言及しています。僕には、宗教的な目覚めの体験はありませんが、「ひとは生命の一部であり、生命に支えられ育まれてきた」そして、さらにいえば「宇宙の一部である」、という言葉は重いです。生命の一部としてこの世に生を受けたこと自体が、生きる意味なのです。人間は高等な脳を得るに至り、生の意味を問わなければ済まなくなりましたが、たとえば雑草にとっては、一個体として、種として、生命体の一部として生を全うすることが、「生きる」ということなのです。
自分の内と外ということにとらわれず、すべてのものの一部である、という意識を持てば、おのずと行動も変わってくるかもしれません。